患者教育がポイントに
University of California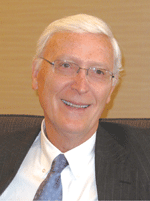
Donald Easton氏に聞く
有効性の観点から脚光を浴びる、新規抗凝固薬。直接トロンビン阻害剤・ダビガトランに続き、第Ⅹa因子阻害剤、リバーロキサバンも臨床現場に登場した。これら薬剤が臨床現場に与えるインパクトを中心に、「ARISTOTLE(Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation)」試験のInvestigatorの1人であり、一過性脳虚血発作(TIA)研究の第一人者でもある、University of CaliforniaのDonald Easton氏に、お話を伺った。
―新規抗凝固薬登場後の現在の米国での治療状況について教えてください。
Easton氏 米国でのダビガトランの浸透は、予想以上にゆっくり進んでいます。実臨床では、予想以上に消化管出血の頻度が高く、全ての患者集団に投与することはできないのが現状です。また、同じ直接トロンビン阻害剤である、キシメラガトランが心筋梗塞の発生上昇のために、開発中止になった経緯があります。そのため、循環器専門医も、心筋梗塞の兆候に注意し、慎重に投与を進めているのではないかと思います。
一方、リバーロキサバンやアピキサバンは、異なるクラス、第Ⅹa因子阻害剤ですから、これより早く臨床現場への浸透が進むのではないかと考えています。
GPは、循環器専門医の処方動向をみて処方を決めると思います。一方、神経内科医では頭蓋内出血を実際に起こした患者さんを診察しています。そのため、頭蓋内出血の頻度が少ないことが特徴とされる、新規抗凝固薬もより早く浸透していくのではないでしょうか。
―「ARISTOTLE」試験の結果についてのご感想をお聞かせください。
Easton氏 この試験結果は、私がこれまでに見た中で、最もポジティブな結果の試験と言わなければならないでしょう。誰もが、虚血性脳卒中と出血性脳卒中を含む、主要評価項目で、ワルファリンに優越性を示したことから、臨床試験の真の勝者だと思うのではないでしょうか。我々医師は、ワルファリンと同様の有効性で、出血の頻度が減少し、薬物相互作用の少ない薬剤の登場をずっと望んできました。そうすれば、ワルファリンは投与しなくてもよいからです。
臨床試験で、有効性において、ワルファリンへの非劣性を示しただけでも、薬剤は“big winner”と言えると思います。さらに、優越性を示したことは大きいのですが、ARISTOTLEでは、さらに頭蓋内出血、死亡率の観点からも非常に良い結果で、あらゆる意味でポジティブな結果だったと言えると思います。
私見ですが、ワルファリンからアピキサバンへと切り替えができない懸念が少しあるとすれば、医療費の側面です。ただ、脳卒中とTIAの二次予防の観点から言えば、これだけ再発を抑制し、ネットクリニカルベネフィットを得ることができれば、費用対効果の面からも明らかに有用な薬剤であると言えると思います。
サブグループ解析は慎重な評価を
―第Ⅹa因子阻害剤にも、すでにリバーロキサバン、今後はエドキサバンなど、複数の薬剤が登場することが期待されています。
Easton氏 もともとどの臨床試験も、ワルファリンが非常に有用な薬剤であるため、ワルファリンへの非劣性を示すことを目的に実施されました。皆、どの薬剤が最適かたずねますが、この答えは現時点では非常に難しく、きちんと回答するにはまだ長い時間が必要だと感じています。
虚血性脳卒中、出血性脳卒中、死亡率…など各評価項目や、サブグループ解析の結果だけが論じられることもありますが、これは非常に危険性を伴うと感じています。忘れてはならないのは、イベントが対象患者の90%以上で発生していない、という点です。そのため、非常に比較が難しいと言えます。
現在のところ、ワルファリンに比べ、虚血性脳卒中を有意に抑制している薬剤はダビガトランだけですが、現在のところ、はっきり言えるのは、どの薬剤も高い虚血性脳卒中の発症抑制効果があると言うことだけではないかと思います。本当の意味で差を見出す必要があるならば、大規模なhead to headの試験を行う必要があると考えます。
―投与回数が臨床現場に与える影響についてのお考えをお聞かせください。
Easton氏 リバーロキサバンは1日1回投与の薬剤で、患者にとっても便利だと思います。ただ、私は、患者が服用を忘れた際に患者を守るという観点からも、1日2回投与の薬剤を好みます。ROCKET AFの結果を見ても、リバーロキサバンの脳卒中、全身性塞栓症の発生は、試験終了後のワルファリンへの切り替えの際に多く起きています。ワルファリンは、半減期が非常に長い薬剤のため、効果発現までの時間がかかるのです。
1日1回の薬剤であれば、1度患者が服用を忘れてしまうと、48時間薬剤を服用しないということにつながります。1日2回の薬剤であれば、この点についての対処がしやすいと言えます。
例えば、糖尿病の薬剤は多くが1日3回投与です。しかし、多くの患者はすぐに学びます。実際、1週間から10日が経過すると、患者が服用に慣れるというデータもあります。ですから、個人的には、1日2回投与であることはそこまで大きなデメリットだとは感じません。
ただ、患者教育は非常に重要になります。“もし、服用を忘れれば、脳卒中になる”とネガティブなことを強調して伝えることも必要かもしれません。